◆不定期日記ログ◆
CATEGORY 考察
- ■2009-08-20
- 不統一なカタカナ
カタカナ語の表記を統一するとき、いつも困るのが「ー」の扱いである。
たとえば「コンピュータ」か「コンピューター」か、という問題だ。
これが正解、という基準は存在しないので、よりどころになりそうなものを探す。
内閣告示の「外来語の表記」によると、
一方、現状で「ー」を省いている用語は、日本工業規格(JIS)の原則であった、
パソコン用語を始め、工学的なものが「ー」を省略するのはこの理由による。
この様式を知らない人が「パソコン用語は最後の長音を省いている」と機械的に認識し、Dataを「データー」と発音してしまったりする被害が出ている。
だが、JISに関係あるかどうかで「ー」の有無を判断すればいいかというと、そう単純ではないので困る。
履物は「スリッパー」ではないし、ぬいぐるみは「テディーベアー」ではない。
「モーター」はよく見かけるが「プロペラー」は見かけない。
基準はサッパリわからないが、慣用化した例外がたくさんある。
これらを統一しようと思っても、そう上手くいくものではない。
我々は無意識に、曖昧に、これを利用して言葉を区別しているからだ。
たとえば、モニタと言えば画面だが、モニターと言えば試用者だ。
ドライバーといえば運転者だが、ドライバと言えば周辺機器だ。
フリーザと言えばポロリだが、フリーザーと言えば伝説のポケモンだ。
ローラーと言えば重いコンダラだが、ローラと言えばヒデキだ。
カタカナ語の発音なんて、もともと原語とかけ離れているのだから、開き直ってこの種の使い分けをもっと広げてもいいと思う。
lighterとwriterのどちらかに「ライタ」という表記が定着していれば、我々はZippoについての記事を書くときに駄洒落をいくつも思いつかずに済んだはずだ。
rockerとlockerのどちらかに「ロッカ」という表記が定着していれば、我々はコインロッカーと間違えてパンクロッカーに荷物を預けたりしないで済んだはずだ。
しかしキャリア(carrier/career 職歴・官僚・運輸・通信・病気)のように、すでに意味が爆裂している例もあるので、あまり効果はないだろうし、定着もしないだろう。
まことに言語は複雑である。
たとえば「コンピュータ」か「コンピューター」か、という問題だ。
これが正解、という基準は存在しないので、よりどころになりそうなものを探す。
内閣告示の「外来語の表記」によると、
英語の語末の-er、-or、-arなどに当たるものは、原則としてア列の長音とし長音符号「ー」を用いて書き表す。
一方、現状で「ー」を省いている用語は、日本工業規格(JIS)の原則であった、
a)その言葉が3音以上の場合には、語尾に長音符号を付けない。
b)その言葉が2音以下の場合には、語尾に長音符号を付ける。
パソコン用語を始め、工学的なものが「ー」を省略するのはこの理由による。
この様式を知らない人が「パソコン用語は最後の長音を省いている」と機械的に認識し、Dataを「データー」と発音してしまったりする被害が出ている。
だが、JISに関係あるかどうかで「ー」の有無を判断すればいいかというと、そう単純ではないので困る。
履物は「スリッパー」ではないし、ぬいぐるみは「テディーベアー」ではない。
「モーター」はよく見かけるが「プロペラー」は見かけない。
基準はサッパリわからないが、慣用化した例外がたくさんある。
これらを統一しようと思っても、そう上手くいくものではない。
我々は無意識に、曖昧に、これを利用して言葉を区別しているからだ。
たとえば、モニタと言えば画面だが、モニターと言えば試用者だ。
ドライバーといえば運転者だが、ドライバと言えば周辺機器だ。
フリーザと言えばポロリだが、フリーザーと言えば伝説のポケモンだ。
ローラーと言えば重いコンダラだが、ローラと言えばヒデキだ。
カタカナ語の発音なんて、もともと原語とかけ離れているのだから、開き直ってこの種の使い分けをもっと広げてもいいと思う。
lighterとwriterのどちらかに「ライタ」という表記が定着していれば、我々はZippoについての記事を書くときに駄洒落をいくつも思いつかずに済んだはずだ。
rockerとlockerのどちらかに「ロッカ」という表記が定着していれば、我々はコインロッカーと間違えてパンクロッカーに荷物を預けたりしないで済んだはずだ。
しかしキャリア(carrier/career 職歴・官僚・運輸・通信・病気)のように、すでに意味が爆裂している例もあるので、あまり効果はないだろうし、定着もしないだろう。
まことに言語は複雑である。
- ■2009-07-15
- 続・だめな選挙
前回の日記の中で、選挙運動の無駄の多さについてひとしきり絶望した。
が、調べてみると、昭和28年にすでに「選挙運動をシンプルにしよう」という試みを実践した候補者がいたことがわかった。
「トラックもマイクも使わず、運動の主力をハガキとポスターに置く」という方針で見事当選したのは、婦人運動家として有名な市川房枝であった。
平塚らいてうと並んで教科書に載ってるレベルの大物じゃないか。
ネームバリューがあったからこそできた作戦かもしれない。だが、定められた選挙費用上限額のわずか16%の出費で済んだという、そのコストパフォーマンスは驚きである。
話は変わるが、与野党ともに政治家の「不透明な収入」が問題に上がることが多い。
マスコミは「政治とカネの問題」と名付けて解決した気になっている感がある。
この類の問題が持ち上がったとき、(秘書が)帳簿をごまかしただの、(秘書が)帳簿の詳細を把握していなかっただのと、「どのような方法で不正に金を手に入れたか」が追求されるのが常である。
この構図がまずおかしい。
国民が知りたいのは「どうしてその金が必要だったのか」ではないのか?
親の財布から金を抜いた子どもを叱責するとき、「どうやって抜いた!」と聞いて何が解決するのか。「何に使った!」が自然だろう。
不正な金の出所を明らかにしても意味がないじゃあないか。金の用途を明らかにし、そんな大金を使わなければならないシステムを改めない限り、どんな規制を作っても抜け出す人間が現れるだろう、というのは悲観的な人間でなくても予想するところである。
しかし本当に、オザワさんやハトヤマさんは何に金を使ったのか?
まさか漢検理事長みたいに、豪邸や石碑を建てるのに使ったのではあるまい。そんなマヌケが党首をやってるハズはない。
素人の考えでまっさきに出てくるのは「選挙」である。これ以上ディープな事例になるとたいてい妄言扱いされてしまうので、妥当なところではないだろうか。
実際、党の公認を得ない完全無所属の候補者は、選挙資金の捻出に苦労するらしい。逆に考えれば、党の公認候補は、党から資金を貰っていることになる。
候補者全員が合理化に動けば、相当な節約の余地が出るのではないか?
大事だと思うのでもう一度書く。
もし政治が腐ってるとしたら、それは選挙が腐ってるからだ。
古いやり方の選挙では、古い考え方の人間しか国会に送り込めない。
だが、そんな絶望的なルールの中で、少しでも効率を考えている候補者がいないか、次の選挙では注視してみるつもりだ。
立候補の際に委員会から渡された選挙七つ道具(事務所や選挙カーや拡声器の表示板など)をつき返して、
「必要ない、この脚のみで選挙区を横断して優勝する」
などというサンドマンみたいな奴が居ないものか(たぶんリタイアするけど)。
が、調べてみると、昭和28年にすでに「選挙運動をシンプルにしよう」という試みを実践した候補者がいたことがわかった。
「トラックもマイクも使わず、運動の主力をハガキとポスターに置く」という方針で見事当選したのは、婦人運動家として有名な市川房枝であった。
平塚らいてうと並んで教科書に載ってるレベルの大物じゃないか。
ネームバリューがあったからこそできた作戦かもしれない。だが、定められた選挙費用上限額のわずか16%の出費で済んだという、そのコストパフォーマンスは驚きである。
話は変わるが、与野党ともに政治家の「不透明な収入」が問題に上がることが多い。
マスコミは「政治とカネの問題」と名付けて解決した気になっている感がある。
この類の問題が持ち上がったとき、(秘書が)帳簿をごまかしただの、(秘書が)帳簿の詳細を把握していなかっただのと、「どのような方法で不正に金を手に入れたか」が追求されるのが常である。
この構図がまずおかしい。
国民が知りたいのは「どうしてその金が必要だったのか」ではないのか?
親の財布から金を抜いた子どもを叱責するとき、「どうやって抜いた!」と聞いて何が解決するのか。「何に使った!」が自然だろう。
不正な金の出所を明らかにしても意味がないじゃあないか。金の用途を明らかにし、そんな大金を使わなければならないシステムを改めない限り、どんな規制を作っても抜け出す人間が現れるだろう、というのは悲観的な人間でなくても予想するところである。
しかし本当に、オザワさんやハトヤマさんは何に金を使ったのか?
まさか漢検理事長みたいに、豪邸や石碑を建てるのに使ったのではあるまい。そんなマヌケが党首をやってるハズはない。
素人の考えでまっさきに出てくるのは「選挙」である。これ以上ディープな事例になるとたいてい妄言扱いされてしまうので、妥当なところではないだろうか。
実際、党の公認を得ない完全無所属の候補者は、選挙資金の捻出に苦労するらしい。逆に考えれば、党の公認候補は、党から資金を貰っていることになる。
候補者全員が合理化に動けば、相当な節約の余地が出るのではないか?
大事だと思うのでもう一度書く。
もし政治が腐ってるとしたら、それは選挙が腐ってるからだ。
古いやり方の選挙では、古い考え方の人間しか国会に送り込めない。
だが、そんな絶望的なルールの中で、少しでも効率を考えている候補者がいないか、次の選挙では注視してみるつもりだ。
立候補の際に委員会から渡された選挙七つ道具(事務所や選挙カーや拡声器の表示板など)をつき返して、
「必要ない、この脚のみで選挙区を横断して優勝する」
などというサンドマンみたいな奴が居ないものか(たぶんリタイアするけど)。
- ■2009-07-14
- だめな選挙
選挙が近いので、普段思っていることを真面目に書く。
もし政治が腐ってるとしたら、それは選挙が腐ってるからだ。
すべての政治家は選挙をクリアしている。
そういう意味では、政治批判の大半は、エアコンからクッセエ風がガンガン出てるのに「ファブリーズしろ!」なんて言ってるようなもので、まずはそのカビたフィルタを交換すべき、という意見が出ないのはおかしい。
選挙がダメなのは、選挙側と被選挙側の「選挙」に対する認識のズレが大きすぎるのが原因だと思う。
選挙運動の大半は、我々が自分たちの代表を選ぶにあたって役に立たない。
たとえば選挙カーや街頭演説は「私は夜勤に従事する人の生活を想像できません」と公言しているようなもので、そういう人々が全国から集まるのが国会である。どう考えても国民の代表とは言えない、レアな人々の集まりだ。
選挙カーは何がしたいのか?
街頭演説は誰にむかって叫んでいるのか?
アレにさく時間、エネルギー、人件費を考えると、どう考えても元がとれるだけの効果はなかろう。
だいたい公職選挙法で「選挙カーの上では、名前とかしか叫んじゃダメ」などと定められているわけで、これはもう遠まわしに「選挙カーを使うな」と言ってるも同然だろう。空気を読んで欲しい。
「選挙カーがうるさいから、来た奴には投票しない」という意見も、決して子どもっぽいワガママではなく、むしろ極めて常識的な判断ではないかと思える。こんな無駄な行為を行う人間が、税金の無駄遣いを抑えられるわけがない。
費用対効果を考えると、現在の選挙活動は無駄ばかりである。無駄な努力というのは、当人以外にとっては多かれ少なかれ「害悪」だ。
なぜ無駄にしかみえない行為を続けるのか?
選挙は一種のエクストリーム・スポーツではないだろうか。
汗だくで街頭演説を続ける候補者の姿を放送するマスコミの姿勢は、スポーツ選手に対するそれに近い。考えてみれば出陣式みたいなことをやるのもスポーツっぽいし、開票速報なんてもう完全にスポーツ中継だと思う。
はたから見て「なぜこんな事をしているんだ?」と不思議に思うのも、「そういうスポーツだから」ということなら納得できる。
選挙がスポーツだとしたら、ルールブック(公職選挙法)はアレも反則、コレも反則でなにひとつ盛り上がる要素のないマイナー格闘技だ。
それなのに「観客動員数が予定の6割に満たない」などといってオロオロするのはまったく馬鹿馬鹿しい話だと感じる。
選挙はスポーツなんかではない、代表を選ぶ大切な民主主義活動だ、というのなら、もっと実のある活動をしてほしい。
たとえば、せっかく候補者を一覧できるポスターボードがあるのに、顔と名前しか書かれていないというのはおかしい。当選したら何に力を入れるのか、そして(特にこれを書く人が誰もいないのが信じられないが)何に力を入れないのか、を記載しておくべきではないのか。
選挙運動は、ポスターと、許可された分のダイレクトメールと、マスコミで演説する機会だけ有効に活用すれば、実質的には十分ではないかと思う。
ていうかこれなら、少ない資金で誰でも立候補できそうな気がする。
お、いっそのこと公職選挙法の全面改正を掲げて立候補するか?
……とチラッと思ったが、どうやら一定割合の票を獲得できなければ預けておいた大金をボッシュートされるという制度があるらしい。
なるほど、二世議員ばかりになるわけだ。
もし政治が腐ってるとしたら、それは選挙が腐ってるからだ。
すべての政治家は選挙をクリアしている。
そういう意味では、政治批判の大半は、エアコンからクッセエ風がガンガン出てるのに「ファブリーズしろ!」なんて言ってるようなもので、まずはそのカビたフィルタを交換すべき、という意見が出ないのはおかしい。
選挙がダメなのは、選挙側と被選挙側の「選挙」に対する認識のズレが大きすぎるのが原因だと思う。
選挙運動の大半は、我々が自分たちの代表を選ぶにあたって役に立たない。
たとえば選挙カーや街頭演説は「私は夜勤に従事する人の生活を想像できません」と公言しているようなもので、そういう人々が全国から集まるのが国会である。どう考えても国民の代表とは言えない、レアな人々の集まりだ。
選挙カーは何がしたいのか?
街頭演説は誰にむかって叫んでいるのか?
アレにさく時間、エネルギー、人件費を考えると、どう考えても元がとれるだけの効果はなかろう。
だいたい公職選挙法で「選挙カーの上では、名前とかしか叫んじゃダメ」などと定められているわけで、これはもう遠まわしに「選挙カーを使うな」と言ってるも同然だろう。空気を読んで欲しい。
「選挙カーがうるさいから、来た奴には投票しない」という意見も、決して子どもっぽいワガママではなく、むしろ極めて常識的な判断ではないかと思える。こんな無駄な行為を行う人間が、税金の無駄遣いを抑えられるわけがない。
費用対効果を考えると、現在の選挙活動は無駄ばかりである。無駄な努力というのは、当人以外にとっては多かれ少なかれ「害悪」だ。
なぜ無駄にしかみえない行為を続けるのか?
選挙は一種のエクストリーム・スポーツではないだろうか。
汗だくで街頭演説を続ける候補者の姿を放送するマスコミの姿勢は、スポーツ選手に対するそれに近い。考えてみれば出陣式みたいなことをやるのもスポーツっぽいし、開票速報なんてもう完全にスポーツ中継だと思う。
はたから見て「なぜこんな事をしているんだ?」と不思議に思うのも、「そういうスポーツだから」ということなら納得できる。
選挙がスポーツだとしたら、ルールブック(公職選挙法)はアレも反則、コレも反則でなにひとつ盛り上がる要素のないマイナー格闘技だ。
それなのに「観客動員数が予定の6割に満たない」などといってオロオロするのはまったく馬鹿馬鹿しい話だと感じる。
選挙はスポーツなんかではない、代表を選ぶ大切な民主主義活動だ、というのなら、もっと実のある活動をしてほしい。
たとえば、せっかく候補者を一覧できるポスターボードがあるのに、顔と名前しか書かれていないというのはおかしい。当選したら何に力を入れるのか、そして(特にこれを書く人が誰もいないのが信じられないが)何に力を入れないのか、を記載しておくべきではないのか。
選挙運動は、ポスターと、許可された分のダイレクトメールと、マスコミで演説する機会だけ有効に活用すれば、実質的には十分ではないかと思う。
ていうかこれなら、少ない資金で誰でも立候補できそうな気がする。
お、いっそのこと公職選挙法の全面改正を掲げて立候補するか?
……とチラッと思ったが、どうやら一定割合の票を獲得できなければ預けておいた大金をボッシュートされるという制度があるらしい。
なるほど、二世議員ばかりになるわけだ。
- ■2009-06-19
- すべてがF
駅のホームってアレ……
プラットフォーム(Platform)だから「フォーム」と書くべきだよな……
「ヴァ」が「バ」になる例とか、「トゥ」が「ツ」になる例とかはよく見るが、「フォ」が「ホ」になるのは珍しいのではないだろうか。
日本人にとって「ファ行」の発音は容易だったのだろうか。他に「F」の音が「ハ行」になっている単語というと、もはや「コーヒー」くらいしか思いつかない。
なにゆえ「フォーム」を「ホーム」にしてしまったのか?
フォークとホークの違いがわからないのでは、おちおちダイエーで買い物できない。
ふと、歴史の教科書に載っている、ある文献のことを思い出した。
戦国時代に出版された、キリシタン版『平家物語』である。
ローマ字っぽく綴られたその本文の中には、「NIFON(日本)」とか「FEIQENO MONOGATARI(平家の物語)」とかいう記述を見ることができる。
宣教師の耳を信用すると、かつては「ハ行」が「ファ行」の発音になっていたらしい。
つまり「ホーム」と書いて「フォーム」と読んでいた可能性は十分ある。
戦国時代にプラットホームがあった可能性は限りなく低いが。
しかしこうなると、別の恐ろしい事実が見えてくる。
戦国時代に「ハ行」が「ファ行」だったとすると、あの猛将・本多忠勝は「ふぉんだふぇいふぁちろう」と名乗っていたことになるではないか。
フォン・ダ・フェイファチロー [Fond de Pfeifer-Thirault](1548~1610年 フランス)
ぜんっぜん猛将っぷりが伝わってこない。
プラットフォーム(Platform)だから「フォーム」と書くべきだよな……
「ヴァ」が「バ」になる例とか、「トゥ」が「ツ」になる例とかはよく見るが、「フォ」が「ホ」になるのは珍しいのではないだろうか。
日本人にとって「ファ行」の発音は容易だったのだろうか。他に「F」の音が「ハ行」になっている単語というと、もはや「コーヒー」くらいしか思いつかない。
なにゆえ「フォーム」を「ホーム」にしてしまったのか?
フォークとホークの違いがわからないのでは、おちおちダイエーで買い物できない。
ふと、歴史の教科書に載っている、ある文献のことを思い出した。
戦国時代に出版された、キリシタン版『平家物語』である。
ローマ字っぽく綴られたその本文の中には、「NIFON(日本)」とか「FEIQENO MONOGATARI(平家の物語)」とかいう記述を見ることができる。
宣教師の耳を信用すると、かつては「ハ行」が「ファ行」の発音になっていたらしい。
つまり「ホーム」と書いて「フォーム」と読んでいた可能性は十分ある。
戦国時代にプラットホームがあった可能性は限りなく低いが。
しかしこうなると、別の恐ろしい事実が見えてくる。
戦国時代に「ハ行」が「ファ行」だったとすると、あの猛将・本多忠勝は「ふぉんだふぇいふぁちろう」と名乗っていたことになるではないか。
フォン・ダ・フェイファチロー [Fond de Pfeifer-Thirault](1548~1610年 フランス)
ぜんっぜん猛将っぷりが伝わってこない。
- ■2009-05-30
- 食パンの食
なぜ「食パン」は「食」という言葉を冠しているのか?
この疑問にとりつかれ、周囲に聞いたり調べたりした結果、いくつかの仮説があるものの決定打はないことがわかった。
・消しパンとの対比説
デッサンなどで使う消しゴム用のパンと区別した、という説。
思わず納得してしまう信憑性をもつトリビアだが、冷静に評価すると怪しい。
パンはもともと食べるものであり、西洋画が入ってきた時にもその価値観は同じだったはず。そんななか、美術というごく一部の世界で使われていた言葉が、一般市民の価値観を凌駕できたかというと疑問が残る。
・「本食パン」説
洋食の基本である、という意味で「本食」と呼ばれ、それが略されたという説。
この説もあちこちで見受けられ、説得力がある。
しかし「基本である」という立場を重視するならば、略したとき「食パン」になるだろうか?「本」のほうが残るべきではないだろうか?
同様の理由で「主食パン」説も受け入れがたい。菓子パンも食べるものだからだ。
・フライパンとの対比説
最初、まったくくだらないと思って却下した説。
しかし前の2つの説と同じ視点で検討すると、意外に悪くない気がする。
資料が見つからないのでまったくの憶測だが、洋食が日本に入ってきたとき、料理人は「食パン」と「フライパン」という2つのパンに出会った。
片方は食べるもので、片方は明らかに食べられないものだ。
料理人が「食パン」と呼びはじめたなら、その料理をいただく一般市民にも定着する可能性はある。
なにより、「パンはパンでも食べられないパンはなーんだ?」という古典的なぞなぞの存在が、この説を後押ししている。
これほど反論の余地が多く、いまや子ども相手でも通用しないであろうなぞなぞが、なぜ生まれ、なぜ生き残っているのか。
こういった歴史的背景があるとすればそれも納得がいく。
まったく事実とは異なると思うが、「納得」が事実に優先することが稀にある。
この疑問にとりつかれ、周囲に聞いたり調べたりした結果、いくつかの仮説があるものの決定打はないことがわかった。
・消しパンとの対比説
デッサンなどで使う消しゴム用のパンと区別した、という説。
思わず納得してしまう信憑性をもつトリビアだが、冷静に評価すると怪しい。
パンはもともと食べるものであり、西洋画が入ってきた時にもその価値観は同じだったはず。そんななか、美術というごく一部の世界で使われていた言葉が、一般市民の価値観を凌駕できたかというと疑問が残る。
・「本食パン」説
洋食の基本である、という意味で「本食」と呼ばれ、それが略されたという説。
この説もあちこちで見受けられ、説得力がある。
しかし「基本である」という立場を重視するならば、略したとき「食パン」になるだろうか?「本」のほうが残るべきではないだろうか?
同様の理由で「主食パン」説も受け入れがたい。菓子パンも食べるものだからだ。
・フライパンとの対比説
最初、まったくくだらないと思って却下した説。
しかし前の2つの説と同じ視点で検討すると、意外に悪くない気がする。
資料が見つからないのでまったくの憶測だが、洋食が日本に入ってきたとき、料理人は「食パン」と「フライパン」という2つのパンに出会った。
片方は食べるもので、片方は明らかに食べられないものだ。
料理人が「食パン」と呼びはじめたなら、その料理をいただく一般市民にも定着する可能性はある。
なにより、「パンはパンでも食べられないパンはなーんだ?」という古典的なぞなぞの存在が、この説を後押ししている。
これほど反論の余地が多く、いまや子ども相手でも通用しないであろうなぞなぞが、なぜ生まれ、なぜ生き残っているのか。
こういった歴史的背景があるとすればそれも納得がいく。
まったく事実とは異なると思うが、「納得」が事実に優先することが稀にある。
- ■2009-05-21
- ワヰウヱヲのこと
「ディズニー」を発音できないお年寄りを見ると、
ここ半世紀で日本語の発音はバリエーションが増えたのだなあと思う。
かつて「Angel」は「エンゼル」であった。
いまや「エンジェル」という発音・表記が一般的であるといって良いだろう。「エンゼル」という表記・発音は、おもちゃの缶詰に関する文脈か、あるいはロサンゼルスなどの固有名詞に使用されるにとどまる。
いつの間にか我々は「ジェ」の発音を手に入れたのだ。
もしこの成長がなかったら、JEROは「ゼロ」と呼ばれるハメになり、それは演歌というよりはB'zであっただろう。
しかし、表記が根付いていても、発音が根付いていない例も見受けられる。
「ウィ」「ウェ」「ウォ」の3つを例に、少し考えてみた。
ゆっくり思い返してみると、我々は「ウィ」と書いて「うい」と発音することが多々ある。
「ウィーク(Week)」は「ういいく」だし、「ウィンドウ(Window)」は「ういんどう」だ。
さすがに「ウィン(Win)」まで短くなってくると「ウィ」に近くなってくる。
「ウィル・スミス」を「ういる・すみす」と発音する人は少数派だろう。
「ウェ」はどうだろうか。
「ウェディング(Wedding)」「ウェハース(Wafer)」「ウェスト(West)」……脳内で発音してみると、どれも「うえ」になることが多い。
「ウェザー・リポート」は「うえ」だが、本名の「ウェス・ブルーマリン」は「ウェ」に近くなる。
いちばん「ウェ」の発音が意識されるのは「ウェブ(Web)」かもしれない。
「ウォ」について考えると、前2つとは大変な違いがある。
「ウォール(Wall)街」「ウォーキング(Walking)」「ウォーター(Water)」など、驚くほど「ウォ」の発音が根付いている例が多い。
若者層でこれらに「うお」の発音を使う人は、もはやいないのではないか?
この定着率、「ヰ」「ヱ」が死亡した今もなお残る「ヲ」の執念のなせるワザだろうか。
全然関係ない話になるが、Waterを「ウォーター」と読んだのはいったい誰なんだろう。
ジョン万次郎は「わら」と教えたはずだが。
こうなると、なぜ「ワ」は「ウァ」にならないのか?という疑問も出てくる。
VとWに密接な関係があるのは字形からも推測できる。
VAを「ヴァ」としたのにWAを「ウァ」にしないのは不公平ではないのか?
今までの人生で「ウァ」の表記をいちばん目にしたのは、10年前の1999年。
『ファイナルファンタジーVIII』のプレイ中である。
アステカ神話のケツァルコアトルをもじった召喚獣「ケツァクウァトル」や、主人公の一人「ラグナ・レウァール」の名前に「ウァ」の表記が登場した。
これほどの「ウァ」を見たのは後にも先にもこのときだけである。
思いかえすに、小学生だった僕に初めて「ヴァ」の発音を要求したのも、
やはりファイナルファンタジーの「シヴァ」だった。
ファイナルファンタジーならきっとやってくれる。
ここ半世紀で日本語の発音はバリエーションが増えたのだなあと思う。
かつて「Angel」は「エンゼル」であった。
いまや「エンジェル」という発音・表記が一般的であるといって良いだろう。「エンゼル」という表記・発音は、おもちゃの缶詰に関する文脈か、あるいはロサンゼルスなどの固有名詞に使用されるにとどまる。
いつの間にか我々は「ジェ」の発音を手に入れたのだ。
もしこの成長がなかったら、JEROは「ゼロ」と呼ばれるハメになり、それは演歌というよりはB'zであっただろう。
しかし、表記が根付いていても、発音が根付いていない例も見受けられる。
「ウィ」「ウェ」「ウォ」の3つを例に、少し考えてみた。
ゆっくり思い返してみると、我々は「ウィ」と書いて「うい」と発音することが多々ある。
「ウィーク(Week)」は「ういいく」だし、「ウィンドウ(Window)」は「ういんどう」だ。
さすがに「ウィン(Win)」まで短くなってくると「ウィ」に近くなってくる。
「ウィル・スミス」を「ういる・すみす」と発音する人は少数派だろう。
「ウェ」はどうだろうか。
「ウェディング(Wedding)」「ウェハース(Wafer)」「ウェスト(West)」……脳内で発音してみると、どれも「うえ」になることが多い。
「ウェザー・リポート」は「うえ」だが、本名の「ウェス・ブルーマリン」は「ウェ」に近くなる。
いちばん「ウェ」の発音が意識されるのは「ウェブ(Web)」かもしれない。
「ウォ」について考えると、前2つとは大変な違いがある。
「ウォール(Wall)街」「ウォーキング(Walking)」「ウォーター(Water)」など、驚くほど「ウォ」の発音が根付いている例が多い。
若者層でこれらに「うお」の発音を使う人は、もはやいないのではないか?
この定着率、「ヰ」「ヱ」が死亡した今もなお残る「ヲ」の執念のなせるワザだろうか。
全然関係ない話になるが、Waterを「ウォーター」と読んだのはいったい誰なんだろう。
ジョン万次郎は「わら」と教えたはずだが。
こうなると、なぜ「ワ」は「ウァ」にならないのか?という疑問も出てくる。
VとWに密接な関係があるのは字形からも推測できる。
VAを「ヴァ」としたのにWAを「ウァ」にしないのは不公平ではないのか?
今までの人生で「ウァ」の表記をいちばん目にしたのは、10年前の1999年。
『ファイナルファンタジーVIII』のプレイ中である。
アステカ神話のケツァルコアトルをもじった召喚獣「ケツァクウァトル」や、主人公の一人「ラグナ・レウァール」の名前に「ウァ」の表記が登場した。
これほどの「ウァ」を見たのは後にも先にもこのときだけである。
思いかえすに、小学生だった僕に初めて「ヴァ」の発音を要求したのも、
やはりファイナルファンタジーの「シヴァ」だった。
ファイナルファンタジーならきっとやってくれる。
- ■2009-05-10
- 湯桶読み
「湯桶(ゆ・トウ)読み」という言葉をなんとかしたい。
湯桶そのものの知名度がなさ過ぎる。
対になる「重箱(ジュウ・ばこ)読み」の重箱は、おせちのシーズンにギリギリ聞く可能性があるし、スミをつつきたがる人がいる限り印象が薄れることはあるまい。
それに比べて湯桶はどうだ。君は湯桶を知っているか?「そば屋でいつも見るじゃん」と即答できる人はなかなか通なレベルに達していると思う。
湯桶読みの代表を任せられる言葉は他にないのか。
せめて重箱レベルの知名度があるものはないのか。
真っ先に思いついたのが「鼻栓(はな・セン)」だったので絶望した。
鼻栓読み……なんかマ行が読みにくそうだな……
他に浮かんだのも「技表(わざ・ヒョウ)」だとか「引数(ひき・スウ)」だとか、一般に流通してない言葉ばかりなので次々と却下した。
「柴犬」を思いついたときはコレだ!と思ったが、実際は「しばいぬ」が正しいのでこれも却下である。惜しい。
結局のところ、「手帳(て・チョウ)」が一番オーソドックスで、無難なような気がする。
将来、電子化が進んで手帳が絶滅する危険もなくはないが、重箱が生きているうちは大丈夫だろう。
なにより「湯桶」と「手帳」は語感が似ていて、しかも「手帳」のほうが強い。
実生活で「ああ、手帳読みね」とサラッと言ってもツッコまれなさそうな自然さがある。
サラッと言って徐々に浸透させてやりたい。
湯桶そのものの知名度がなさ過ぎる。
対になる「重箱(ジュウ・ばこ)読み」の重箱は、おせちのシーズンにギリギリ聞く可能性があるし、スミをつつきたがる人がいる限り印象が薄れることはあるまい。
それに比べて湯桶はどうだ。君は湯桶を知っているか?「そば屋でいつも見るじゃん」と即答できる人はなかなか通なレベルに達していると思う。
湯桶読みの代表を任せられる言葉は他にないのか。
せめて重箱レベルの知名度があるものはないのか。
真っ先に思いついたのが「鼻栓(はな・セン)」だったので絶望した。
鼻栓読み……なんかマ行が読みにくそうだな……
他に浮かんだのも「技表(わざ・ヒョウ)」だとか「引数(ひき・スウ)」だとか、一般に流通してない言葉ばかりなので次々と却下した。
「柴犬」を思いついたときはコレだ!と思ったが、実際は「しばいぬ」が正しいのでこれも却下である。惜しい。
結局のところ、「手帳(て・チョウ)」が一番オーソドックスで、無難なような気がする。
将来、電子化が進んで手帳が絶滅する危険もなくはないが、重箱が生きているうちは大丈夫だろう。
なにより「湯桶」と「手帳」は語感が似ていて、しかも「手帳」のほうが強い。
実生活で「ああ、手帳読みね」とサラッと言ってもツッコまれなさそうな自然さがある。
サラッと言って徐々に浸透させてやりたい。
- ■2009-05-07
- きららクイーン
仕事で、大量の名前が載っている名簿をパラパラ見ていたところ、
「き」の段に「雲母さん」がいた。
「き」の段にいたということは、当然「きらら」と読む姓なのだろう。
きららさんご一家……もう何をやってもメルヘンチックな印象しか与えない運命だ。
「たばこさん」に出会ったとき以上の衝撃だ。
こういう稀姓は自己紹介でいきなり話のタネになるので便利かもしれない。一生同じネタを繰り返すハメになる煩わしさと差し引いてどちらが勝るかはわからないが。
稀姓が珍しく印象深いのは稀な一族だからであって、同じ効果を狙って子どもに妙な名前をつける親は地獄に投げ込まれるべきだとも思う。
「き」の段に「雲母さん」がいた。
「き」の段にいたということは、当然「きらら」と読む姓なのだろう。
きららさんご一家……もう何をやってもメルヘンチックな印象しか与えない運命だ。
「たばこさん」に出会ったとき以上の衝撃だ。
こういう稀姓は自己紹介でいきなり話のタネになるので便利かもしれない。一生同じネタを繰り返すハメになる煩わしさと差し引いてどちらが勝るかはわからないが。
稀姓が珍しく印象深いのは稀な一族だからであって、同じ効果を狙って子どもに妙な名前をつける親は地獄に投げ込まれるべきだとも思う。
- ■2009-04-23
- ソース出せ
「しょうゆ顔」「ソース顔」というカテゴライズが気になる。
調べてみると、1988年の流行語大賞らしい。
1988年!昭和63年!光GENJIのお兄さんたちがローラースケートを装着して、壊れそうなものばかり集めてしまっていた頃じゃないか!
それなら「ソース=洋風」といういささか古臭い連想も頷ける。
去年の流行語すら思い出せないこのご時世に、20年も前の流行語が生きているとは驚いた。
それはさておき、気になるのは「ソース」のとらえかたである。
しょうゆも立派なソースだし、サラダドレッシングもトマトケチャップもソースの一種だ。
「ソース」と名のつくものだけでも、ここ20年で様々なものが食卓に入ってきた。
それなのにウスターソース類のみをさして「ソース」と呼ぶのはいかがなものか?
だが、よく考えたら「ケチャップ」といえばトマトケチャップのことをさすし、
「ドレッシング」といえばサラダドレッシングのことをさす。
調味料界では珍しい事象ではなかった。
自分はとんかつにもエビフライにも目玉焼きにもソースはかけない主義だ。
他の数々のソースの中から、ウスターソースから「ソース総称権」を奪う、新鋭のソースが頭角を現してくることを期待する。
調べてみると、1988年の流行語大賞らしい。
1988年!昭和63年!光GENJIのお兄さんたちがローラースケートを装着して、壊れそうなものばかり集めてしまっていた頃じゃないか!
それなら「ソース=洋風」といういささか古臭い連想も頷ける。
去年の流行語すら思い出せないこのご時世に、20年も前の流行語が生きているとは驚いた。
それはさておき、気になるのは「ソース」のとらえかたである。
しょうゆも立派なソースだし、サラダドレッシングもトマトケチャップもソースの一種だ。
「ソース」と名のつくものだけでも、ここ20年で様々なものが食卓に入ってきた。
それなのにウスターソース類のみをさして「ソース」と呼ぶのはいかがなものか?
だが、よく考えたら「ケチャップ」といえばトマトケチャップのことをさすし、
「ドレッシング」といえばサラダドレッシングのことをさす。
調味料界では珍しい事象ではなかった。
自分はとんかつにもエビフライにも目玉焼きにもソースはかけない主義だ。
他の数々のソースの中から、ウスターソースから「ソース総称権」を奪う、新鋭のソースが頭角を現してくることを期待する。
「鼻血」は「鼻+血」なので「はなぢ」である。
「はなじ」ではない。
しかし「地面」に代表されるように、この使い分けの根拠は薄弱である。
たとえば「稲妻」は「稲+妻」なので「いなづま」だったハズだが、
広辞苑先生は「いなずま」のみを採用している。
こういうとき妙に頼りになるのがATOK先生である。
「はなじ」で変換しようとすると「鼻血《はなぢの誤り》」と赤を入れてくる。
さて前述の「いなづま」はどうかというと、さすがATOK先生、
「いなづま」でも「いなずま」でも「ゆうづう」をきかせて変換してくれる。
俺の中で新しいスタンダードが生まれた。
「はなじ」ではない。
しかし「地面」に代表されるように、この使い分けの根拠は薄弱である。
たとえば「稲妻」は「稲+妻」なので「いなづま」だったハズだが、
広辞苑先生は「いなずま」のみを採用している。
こういうとき妙に頼りになるのがATOK先生である。
「はなじ」で変換しようとすると「鼻血《はなぢの誤り》」と赤を入れてくる。
さて前述の「いなづま」はどうかというと、さすがATOK先生、
「いなづま」でも「いなずま」でも「ゆうづう」をきかせて変換してくれる。
俺の中で新しいスタンダードが生まれた。
- ■2009-03-27
- 朝○暮○
【朝三暮四】(ちょうさんぼし)
むかしむかし中国にサル好きのおっさんがいました。
おっさんはサルにエサをやり、サルもおっさんを慕って集まりました。
ある日、おっさんは経済的に苦しくなり、エサを減らなくてはならなくなりました。
おっさんは、翌朝、サルたちを集めてモンキー語で言いました。
「すまないが、お前たちのエサを朝3つ夜4つに減らしたい」
するとサルたちはモンキー語ではげしい非難を浴びせました。おっさんは
「わかった、ならば朝は4つに増やそう。そのかわり夜は3つね」
と言いました。サルたちはそれを聞くとスゲェ喜んで納得しました。
このように、目先の利益にとらわれて全体のことを見落とすことを、
「朝三暮四」といいます。
思うに、このサルたちは「朝令暮改」という故事成語を知っていたのではないか?
だとすれば貰えるときに貰っておく姿勢は評価できる。
むかしむかし中国にサル好きのおっさんがいました。
おっさんはサルにエサをやり、サルもおっさんを慕って集まりました。
ある日、おっさんは経済的に苦しくなり、エサを減らなくてはならなくなりました。
おっさんは、翌朝、サルたちを集めてモンキー語で言いました。
「すまないが、お前たちのエサを朝3つ夜4つに減らしたい」
するとサルたちはモンキー語ではげしい非難を浴びせました。おっさんは
「わかった、ならば朝は4つに増やそう。そのかわり夜は3つね」
と言いました。サルたちはそれを聞くとスゲェ喜んで納得しました。
このように、目先の利益にとらわれて全体のことを見落とすことを、
「朝三暮四」といいます。
思うに、このサルたちは「朝令暮改」という故事成語を知っていたのではないか?
だとすれば貰えるときに貰っておく姿勢は評価できる。
- ■2009-03-07
- 白日の下に
バレンタインデーは製菓業界の思惑で始まった。
が、それを牽引して文化にまで高めたのは、決して製菓業界の広告費の力ではない。
ホワイトデーというイベントのあやふやさがそれを示している。
ホワイトデーとは何を贈る日なのか?
クッキーなのか、マシュマロなのか、キャンディーなのか…
「バレンタインデーといえばチョコ」という揺るがないイメージとは真逆だ。
ホワイトデーの設定が固まらないのはなぜか?
菓子以上のお返しを期待する人間が多いからだ!
チョコを贈って菓子以上のものを貰おうという魂胆の人間がいて、
菓子以上のものを買ってもらいたい業界がたくさんあるから、
製菓業界がどんなにクッキーだキャンディだと叫んでも圧殺されるのだ。
愛の名を借りてバレンタインデーとホワイトデーを金勘定で牽引する連中は、聖バレンチノによって地獄に投げ込まれるであろう。
そもそも愛は奪うでも与えるでもなくて気が付けばそこにあるものではなかったのか!
好意100%の本命チョコを贈る場合、それが本当に好意100%によるものなら……
当然、対価は期待しないはず!
街の風に吹かれて歌いながら妙なプライドは捨ててしまえばいい。
そして一ヶ月ごしに100%の好意をやりとりする平和な日になればいい。
しかし不思議なのは「三倍返し」の風習である。
これを言い出した人間は何を考えていたのだろう?
あからさまな欲望を晒しておきながら、たかだかチョコの三倍の値段のもので満足するあたり、すごく庶民的なのかもしれない、が……
そんな頭悪い風習がこんなに広まるとは思えない。何かあるはずだ。
守備に入った軍を攻め落とすには三倍の兵力が要る。
これを攻撃三倍の法則という。
チョコで兵力を見せておいて「さあ私を落としてご覧なさい」という主張をしているのかもしれない。まったく油断ならない日だ。
が、それを牽引して文化にまで高めたのは、決して製菓業界の広告費の力ではない。
ホワイトデーというイベントのあやふやさがそれを示している。
ホワイトデーとは何を贈る日なのか?
クッキーなのか、マシュマロなのか、キャンディーなのか…
「バレンタインデーといえばチョコ」という揺るがないイメージとは真逆だ。
ホワイトデーの設定が固まらないのはなぜか?
菓子以上のお返しを期待する人間が多いからだ!
チョコを贈って菓子以上のものを貰おうという魂胆の人間がいて、
菓子以上のものを買ってもらいたい業界がたくさんあるから、
製菓業界がどんなにクッキーだキャンディだと叫んでも圧殺されるのだ。
愛の名を借りてバレンタインデーとホワイトデーを金勘定で牽引する連中は、聖バレンチノによって地獄に投げ込まれるであろう。
そもそも愛は奪うでも与えるでもなくて気が付けばそこにあるものではなかったのか!
好意100%の本命チョコを贈る場合、それが本当に好意100%によるものなら……
当然、対価は期待しないはず!
街の風に吹かれて歌いながら妙なプライドは捨ててしまえばいい。
そして一ヶ月ごしに100%の好意をやりとりする平和な日になればいい。
しかし不思議なのは「三倍返し」の風習である。
これを言い出した人間は何を考えていたのだろう?
あからさまな欲望を晒しておきながら、たかだかチョコの三倍の値段のもので満足するあたり、すごく庶民的なのかもしれない、が……
そんな頭悪い風習がこんなに広まるとは思えない。何かあるはずだ。
守備に入った軍を攻め落とすには三倍の兵力が要る。
これを攻撃三倍の法則という。
チョコで兵力を見せておいて「さあ私を落としてご覧なさい」という主張をしているのかもしれない。まったく油断ならない日だ。
- ■2009-02-06
- 魚へん
鯵 鰯 鰻 鰹 鮭 鯛 鮪 鮃 鮹 鰕 鰤
いずれも食材として身近な魚の名前だ。
魚の名前を示す「魚へんの漢字」は多々あれど、これらは常用漢字表には含まれていない。魚に限らず、こういうあまり熟語を作らないタイプの漢字はだいたいそうだ。
そんな中、堂々と常用漢字表に含まれているものがある。
「鯨」 である。
分類上では魚ではないが、他の魚介類をおさえて常用の名を欲しいままにしている。
このあたりからも、いかに日本人が鯨を必要としてきたがが伝わってくるだろう。
海のテロリストたちも、目先の寄付団体ばかりにとらわれず、このあたりの文化をちっとは考慮していただきたい。
しかし現在、「鯨」という字が他の魚介類より常用されているかというと、怪しい。
今もっとも使われている魚はなんだろう?
ネットだけに限定していえば「鯖」ではないか?
たかがスラングかもしれない。だが馬鹿にはできない。
「パリ」のことを「巴里」と書いた時代もあった。
漢字字典によっては「英」の項に「イギリス」と書かれていたりする。
「鯖」の項に「サーバー」の意味が追加される日が、来ないとは言えない。
ぜひ鯖には頑張ってほしい。
いずれも食材として身近な魚の名前だ。
魚の名前を示す「魚へんの漢字」は多々あれど、これらは常用漢字表には含まれていない。魚に限らず、こういうあまり熟語を作らないタイプの漢字はだいたいそうだ。
そんな中、堂々と常用漢字表に含まれているものがある。
分類上では魚ではないが、他の魚介類をおさえて常用の名を欲しいままにしている。
このあたりからも、いかに日本人が鯨を必要としてきたがが伝わってくるだろう。
海のテロリストたちも、目先の寄付団体ばかりにとらわれず、このあたりの文化をちっとは考慮していただきたい。
しかし現在、「鯨」という字が他の魚介類より常用されているかというと、怪しい。
今もっとも使われている魚はなんだろう?
ネットだけに限定していえば「鯖」ではないか?
たかがスラングかもしれない。だが馬鹿にはできない。
「パリ」のことを「巴里」と書いた時代もあった。
漢字字典によっては「英」の項に「イギリス」と書かれていたりする。
「鯖」の項に「サーバー」の意味が追加される日が、来ないとは言えない。
ぜひ鯖には頑張ってほしい。
- ■2008-12-23
- ゼロゼロ
コカ・コーラゼロが、ちょっと前からキャンペーンを行っている。
その名も「Coca-Cola zero zero 7」。
ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ。
ジェームズ・ボンドの「007」は「ダブルオーセブン」が公式なんであって、「ゼロゼロセブン」って読むとマニアから「それはサイボーグ戦士のことだ」とか「オヤジくさい読み方すんな」とか、熾烈なツッコミを受けるのではなかったか!?
日本コカ・コーラが正面きってゼロゼロと読んだということは、
もはや公式がダブルオーと読んでいることなどは問題ではなく、
一般に日本人が読みがちなゼロゼロこそが勝者だということか!?
これからは「ゼロゼロセブン」と読んでも白眼視されない世の中が来るんだな!?
「機動戦士ガンダムゼロゼロ」と読んでも、「ガンダムW」に怒られないんだな!?
恋のテレフォンナンバーもシックス・セブン・ゼロゼロで繋がるんだな!?
……まあ繋がると思うけど!
世の中を動かすのは正しさじゃない!
楽しさ(楽さ)だ!
より快いと思うほうに正義は流れるのだ!
その名も「Coca-Cola zero zero 7」。
ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ。
ジェームズ・ボンドの「007」は「ダブルオーセブン」が公式なんであって、「ゼロゼロセブン」って読むとマニアから「それはサイボーグ戦士のことだ」とか「オヤジくさい読み方すんな」とか、熾烈なツッコミを受けるのではなかったか!?
日本コカ・コーラが正面きってゼロゼロと読んだということは、
もはや公式がダブルオーと読んでいることなどは問題ではなく、
一般に日本人が読みがちなゼロゼロこそが勝者だということか!?
これからは「ゼロゼロセブン」と読んでも白眼視されない世の中が来るんだな!?
「機動戦士ガンダムゼロゼロ」と読んでも、「ガンダムW」に怒られないんだな!?
恋のテレフォンナンバーもシックス・セブン・ゼロゼロで繋がるんだな!?
……まあ繋がると思うけど!
世の中を動かすのは正しさじゃない!
楽しさ(楽さ)だ!
より快いと思うほうに正義は流れるのだ!
- ■2008-12-09
- 「徳」と「得」
良い子のみんな!早起きは三文の得というが
三文とは今の金にすると60円ぐらいだそうだ
寝てる方がマシだな。(AA略)
もし60円の損で寝坊できるとしたら俺は喜んで料金を支払う。
月額1800円で寝坊し放題。このビジネスは間違いなく流行る。
だが、どうやら「三文の得」という言い方は怪しいようだ。
わりと広く使われているが、手元の広辞苑先生はかたくなに「早起きは三文の徳」とおっしゃっている。
誤用なのか?
「お徳用」のように、「徳」と「得」はわりと互換性がある漢字だ。
簡単に誤用と言い切ることはできない。
だが本当にこれが誤用で、「獲得」の「得」ではなく、「人徳」の「徳」だとすると、このことわざは何を示しているのか?
ここで「三文」という言葉に注目する。
「二足三文」のように、三文は「きわめて安い」の意味で使われることもある。
きわめて安い…人徳?
全然褒めてねえじゃん!!
つまりこのことわざは、
「へぇー早起きするなんてイマドキ偉いッスねェー」
と上から目線で馬鹿にしているのではないか!?
まだ60円のほうがマシな解釈だ!!
- ■2008-10-23
- 大合併時代
地図の上 富士川町に 黒々と 墨をぬりつつ 秋風を聞く
11月から年明けにかけて、静岡県から4つの町が消滅する。
ここ数日は、それにともなう地図の地名変更の作業に明け暮れており、つい啄木気分になってしまった。
だが、まだまだ市町村合併の勢いは衰えを知らない。
早くも東端、伊豆半島で次なる合併が画策されている。
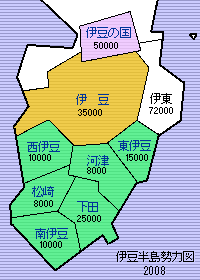
伊豆半島勢力図(数字は戦闘力)
合併につきものなのが新市名募集だが、公募の結果、「伊豆下田市」がいまのところ人気だそうだ。
…嘆かわしい!
そもそもの問題は、2004年の合併で図々しくも「伊豆」を総称した伊豆市の存在なのだ。
かわいそうに、2005年に生まれた伊豆の国市は、「伊豆」という名称を捨てることなどできるはずもなく、このような珍市名を晒す結果になってしまった。
南伊豆地区も、伊豆市に隷属するような名前を使ってはならぬ!
だいたい市名が長いと郵便を出しにくいだろ!
なんかなし崩し的に「伊豆下田市」になってしまいそうな気もするが、
名前候補の中には「黒船市」「開国市」なんていう相当ルナティックなものもあった。
伊豆市から始まった市名の迷走に終止符を打つには、これくらい思い切った市名でないといけないのかもしれない。
